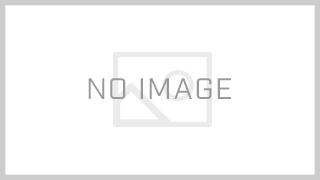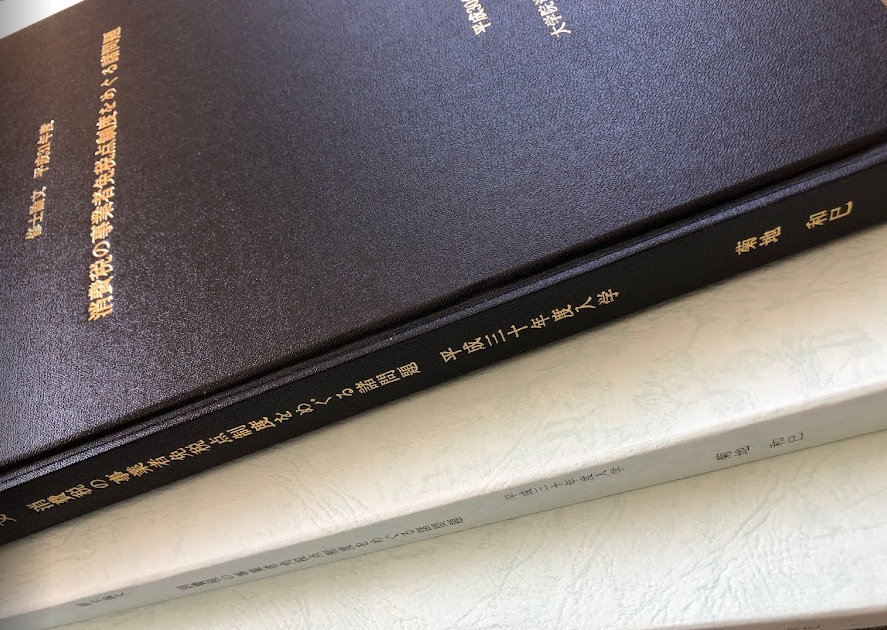
1.徴税コストとは、「租税の執行に伴い発生する費用」であり、「課税庁側に発生する税務執行費用と、納税者等が負担する納税協力費用に分けることができる[133]」という。前項で納税協力費については扱ったため、本項では、税務執行費用について取り上げることにする。
そして、税務執行費用とは、「徴税事務執行にかかる一切の費用をいい、業務の執行過程で支出する税務職員の人件費、交通費、物件費等の他、税制を周知徹底させるための費用などが含まれる[134]」という。
また、西山教授によると、徴税コストについて、国内レベルでの調査研究は、十分に行われていないという。その理由は、継続的かつ信頼できる公式データがほとんど存在しない[135]ことによる。わが国では、国税庁の平成15年版の「日本における税務行政」における徴税コストの記載を最後に公表されたデータが入手できない状況になっている。
そのような状況下ではあるが、先の大野教授と芥川税理士による研究では、平成元年から平成13年までの公表データを元に、税目当たりの税務執行費用について算出している。

この表から、「基幹税制たる主要3税[136]のうち、消費税は税務執行費用が他の諸税(筆者注:間接諸税)[137]と同様に低い[138]」ことが見て取れる。
データは平成13年までであり、その後の平成16年には、免税点は1000万円に切り下げたことにより消費税の申告件数が急増したことや、事業者免税点制度や簡易課税制度において数度の改正が行われたことによる周知費用等により、税務執行費用が増加した可能性が高いものの、現行制度の下では、「源泉所得税に匹敵する『メインテナンス費用のかからない租税』[139]」であることに変わりはないものと思われる。
2.免税点と徴税コストの問題について、増井教授はOECD[140]の2014年版報告書を紹介し、閾値[141]の水準は「各国の間でコンセンサスはない。多くの場合、閾値のレベルは、納税協力コスト・税務行政コストを最小化することと、税収を危うくし競争にひずみを与えることと間での、トレード・オフの結果である[142]」としている。そして、閾値の設定について、「VAT[143]が登場したころの専門家の通常の助言は、VAT事業者登録の基準となる数値(通常それは年間売上高として定義される)をできる限り低く設定すべきである、というものであった。これによって潜在的に課税できる取引をすべてVATの対象にできると考えられた。この助言は、執行コストと納税協力コストがゼロであることを黙示的に前提としており、そこからは理想の閾値はゼロであることになる」という考えであったが、「時間の経過とともにこの通念は変化した」という。これは「多くの国で、少数の大規模事業者だけでVAT税収の8割から9割を納付している。これに対し、小規模事業者を納税義務者としても、執行コストと納税協力コストが大きくなるだけで、追加的に得られる税収は少ない。(中略)かなり高水準の閾値を設けるべきであるということが新たな通念になった。小魚を追うのではなく、大きな鯨を追うべきである[144]」というのである。
3.増井教授が紹介する海外専門家の「小魚ではなく大きな鯨を追え」という視点は、斬新であり、何かとコストパフォーマンスを重視する現代人の経済感覚的にも受け入れやすいものではある。ただし、消費税率が10%と2桁の税率となり、今後も更なる税率アップが予想され、今まで以上に国の基幹税としての役割が期待される消費税について、全事業者のうち約6割が免税事業者[145]とされる状況は、国民感情を思うと課税の公平性の観点から問題があると思われる。
また、徴税コストについても、コンピュータ化・電子申告化・IT化が浸透し、かつそれらの技術が加速度的に進化している現在において、従来同様の「申告件数増=徴税コスト増」と考える人海戦術的な発想[146]でコストを計算することは、時代にそぐわない、と筆者は思料する。徴税コストの問題にも、新しい時代の新しい方法を導入すべきであり、後の章で外国の事例を元に、その方法を探ってみることとする。
4.本節では、事業者免税点制度における益税問題について、消費者・事業者・徴税者という3者の視点から検討を行ってきた。消費税法の導入から30年の時を経て、税率の変更や細かな改正があり、国民の税への理解や浸透があり、またパソコンをはじめとする加速度的な技術革新がある中で、導入当初の趣旨が見直されぬままに放置されている感が深い、現在の事業者免税点制度について、見直しの必要性を改めて感じさせる内容であった。
[133] 大野裕之・芥川浩一「消費税の簡素性:~税務執行費用の推計と他税との比較~」 東洋大学経済研究会29巻1号(2003年12月)2~3頁
[134] 大野裕之・芥川浩一 前掲(注)133 4頁
[135] 西山由美「消費税のコスト-徴税コストとコンプライアンス・コスト」 税理VOL.57No.11(2014年9月)88頁
[136] 法人税・所得税・消費税の3税をいう。
[137] 間接諸税とは、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方道路税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税及び電源開発促進税をいう。(国税庁HPより)
[138] 大野裕之・芥川浩一 前掲(注)133 8頁(表は9頁)
[139] 西山由美 前掲(注)135 94頁
[140] Organization for Economic Co-operation Development の略で、日本語で経済協力開発機構という。国際経済全般について協議することを目的とした国際機関で、別名は「世界最大のシンクタンク」。欧米諸国・米国・日本など34か国で構成されている。
(外務省HPより)
[141] Thresholdの訳語。 日本の小規模事業者の免税点に相当するもの。
[142] 増井良啓「終章 日本の消費税はどこへいくか-国際比較からの展望」 日税研論集第70号 日本税務研究センター(2017年1月)531頁
[143] Value Added Tax の略。付加価値税と訳される。日本の消費税に相当するもの。20世紀生まれの新しい税制。特に欧州各国は、日本に先行して導入しているため、参考になる点が多い。
[144] 増井良啓 前掲(注)142 541~542頁
[145] 第198回国会衆議院財務金融委員会議事録第2号(2019年2月19日)20頁
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=119804376X00220190219&page=1&spkNum=0¤t=1 最終アクセス2020年1月13日
麻生財務大臣の答弁「平成29年度の課税事業者の数は317万者であり、免税事業者数は(財務省としては把握していないものの)総務省の平成27年国勢調査等を元に試算すると488万者と推計される」から、約60.6%が免税事業者である実態が明らかになった。また、同答弁で、業種別の免税事業者の割合は、サービス業関係が35%、農林水産関係が18%、建設業関係が13%、小売業関係が10%と試算されていることも明らかになった。
[146] 八田達夫『消費税はやはりいらない』 東洋経済新報社(1994年12月)では、「フランスでは益税の出ない付加価値税を採用するために、1960年から88年までに税務職員を6000人から30万人に実に50倍に増やした。それによって免税点を年売上高180万円に抑えて益税の発生を防いでいる」という例が紹介されている。