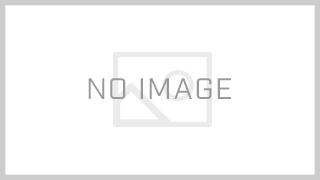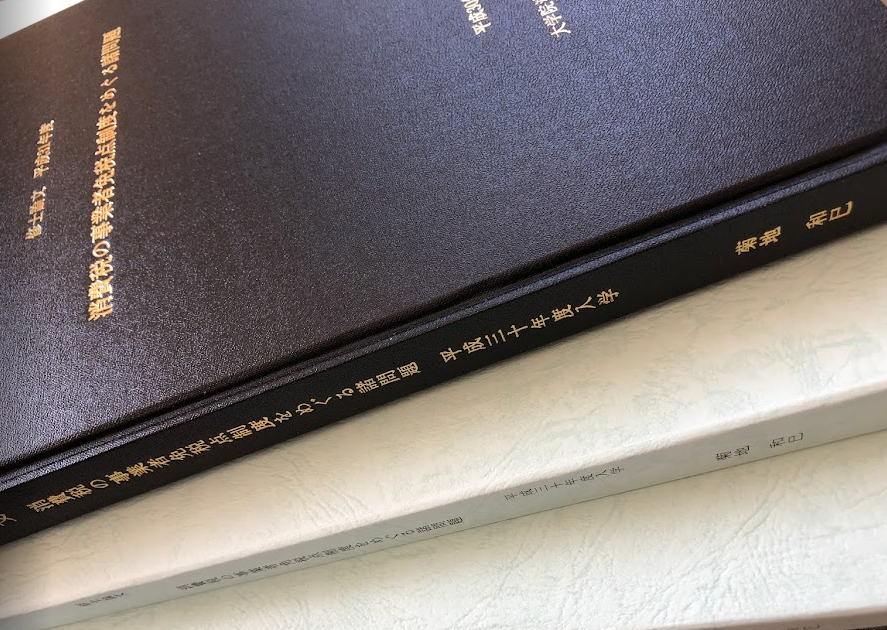
1.平成23年度改正では、「特定期間による納税義務の免除の特例」に関する法案が成立し、従来の基準期間による判定に加えて、特定期間[203]による判定が加えられたことにより、2年間のタイムラグが、1年間に狭まる点で評価することができる。また、この改正による増収額は、財務省によると、年間27億円[204]になることも評価できよう。その一方で、この改正は課税事業者になるのが早まっただけの改正であり、「課税の適正化」の趣旨と矛盾する内容であるとする説があることは前述した[205]。
この点で、中島税理士は「免税事業者の要件の見直しは、規制措置(免税事業者⇒課税事業者)と平仄を合わせるためには緩和措置(課税事業者⇒免税事業者)も必要」であるとして、課税売上高が「上半期で500万円以下の課税事業者に対する見直し(課税事業者⇒免税事業者)[206]」を提言している。
この提言は、業績不振で資金繰りに苦しむ小規模事業者にとっての救いの声となるように思われる。仮に、事業者免税点制度に補助金的性質を認めるとするのであれば、このような事業者にこそ、適用されるべきである。ただし、「課税売上高が上半期で500万円」という基準は、売り上げの計上時期を遅らせる等の操作によって、調整可能であることから、新たな租税回避的なスキームを生む危険性をはらんでいる。解決策は、後に譲ることにして、本改正の問題点をもう一つ見ていく。
2.本改正により、新たに設立された法人の第1期における事業年度の月数が8カ月以上であれば、第2期目から消費税の納税義務は免除されないことになり、改正により益税解消の効果があったといえる。しかし、特定期間の例外規定として、前事業年度が短期事業年度[207]に該当する場合には、前々事業年度開始の日以後6月の期間を特定期間とすることとされている。この例外規定により、新たに設立された法人の第1期における事業年度を7月以下にすれば、「特定期間が存在しないことになり、改正前と同様に設立から2年間納税義務が免除され、益税解消の効果が少ないといえる(設立第1期の期間は7月以下に制限される効果はある)[208]」ものの、

上記の図[209]で確認できる通り、前事業年度は7カ月、その事業年度は12か月の免税メリットを享受することになり、このケースでは、最小でも1年7か月間は免税期間を取得できることから、新たに設立された法人に設立1期目は7か月間で決算期変更をすることをすすめる税理士サイトが散見される状況である。こうして、どんなに事業規模が大きい法人であっても、決算期変更をして、設立1期目を7か月間にするだけで、免税メリットを、改正後も最小でも1年7カ月間の免税期間を享受することができた。その結果、この改正の効果をそぐ抜け道になってしまった[210]。
3.また、当改正では、課税売上高に変えて、人件費等により判定する方法が選択できること[211]になったことも注目に値する。その趣旨は「給与等の金額であれば、売上高との相関性が高く、また、事業者は所得税法により給与支払い明細書の交付義務があり(所法231①)、かつ、源泉徴収義務者は源泉所得税を毎月あるいは6月ごとに納付していること等から、その支払額を把握することが一般的に容易と考えられること等を踏まえ、事業者の事務負担に配慮する観点から設けられたもの[212]」とされている。
選択適用とされたことにより、特定期間における課税売上高が優に1000万円を超える事業者であっても、特定期間における給与等の合計額が1000万円以下であれば、当規定が適用されないことになるため、多くの事業者は、この人件費基準を採用することで、本改正をすり抜けている。確かに給与等の金額は、「把握することは容易」ではあるものの売上高との相関性という点で、業種により異なるにせよ、給与等が売上高を上回ることはほぼ無いであろうし、むしろ実務家の筆者の感覚では、かなりの開きがあるように思われる。
この点について公表データを用いて試算を試みると、売上高に対する人件費の割合を売上高人件費率といい、財務総合政策研究所の数字によると、2015年度の全業種の売上高人件費率の平均値は、14%程度[213]であった。仮に半年間の人件費合計が1000万円の企業を想定し、そこから売上高を逆算すると、7000万円程度となり、年換算すると1億4000万円程度という金額になってしまう。つまり、事業者にとっては、売上高基準ではなく、人件費基準を採用した方が圧倒的に有利な結果になる、ということである。
このような事実があるために、免税点制度における対象者の引き締め効果を狙った筈の「改正の趣旨と合致していない[214]」とする声もあり、この批判は説得力があると思われる。
4.本改正は、特定期間という判定期間を設けたことで、より機動的に免税事業者の判定を行うことができるようになった点で、評価に値する。
その一方で、従来の免税点制度では、売上高基準で事業規模を判定してきたところに、本改正だけ、唐突に人件費基準との選択適用を認めてしまったこと、また、そのことにより改正の効果が削がれてしまったこと、短期事業年度という例外を設けてしまったために、2年間の免税メリットを1年間に圧縮するはずの規定が、1年7カ月の免税メリットに圧縮するだけの抜け道を残してしまったことをもって、本改正については、若干踏み込みが不足しており、「改正の目的を十分に果たすまでには至っていない[215]」という印象は否めない。
[203] 法第9条の2によると特定期間とは「個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日までの期間」であり、法人は、「前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(『短期事業年度』という)を除く)開始の日以後6月の期間」
[204] 財務省HP 「平成23年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/23zougenshuu.htm 最終アクセス2020年1月13日
[205] 本稿24~25頁
[206] 中島孝一「消費税の改正とその影響」 税経通信VOL.66No.4(2011年3月)135~136頁
[207] 法第9条の2第4項 事業年度が7月以下であるもの等をいう。
[208] 中島孝一「新設法人に対する消費税の更なる規制措置の方向性」 Monthly Report No.38 ミクロ情報サービス(2012年3月)32頁
[209] 前掲(注)208の論文の図をもとに筆者が作成した。
[210] 仮に、短期事業年度といった制度を作るのであれば、7か月という決して短くはない期間ではなく、文字通りの短期で、3か月程度といった制度設計の方向性も考えられたのではないだろうか。
[211] 法第9条の2第3項
第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第1項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払った所得税法231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令では定めるものの合計額をもって、第1項の特定期間における課税売上高とすることができる。
[212] 斎須朋之他 前掲(注)28 647頁
[213] 財務総合政策研究所HP キーワードで見る法人企業統計より
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/keyword/keyword_05.pdf
最終アクセス 2020年1月6日
[214] 秋山高善 前掲(注)42 164頁
[215] 矢頭正浩「特定新規設立法人の納税義務免除の特例(法12の3)」 税務弘報64巻12号(2016年11月)32頁