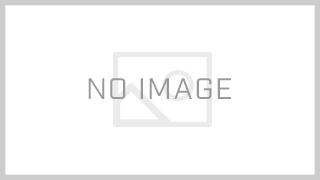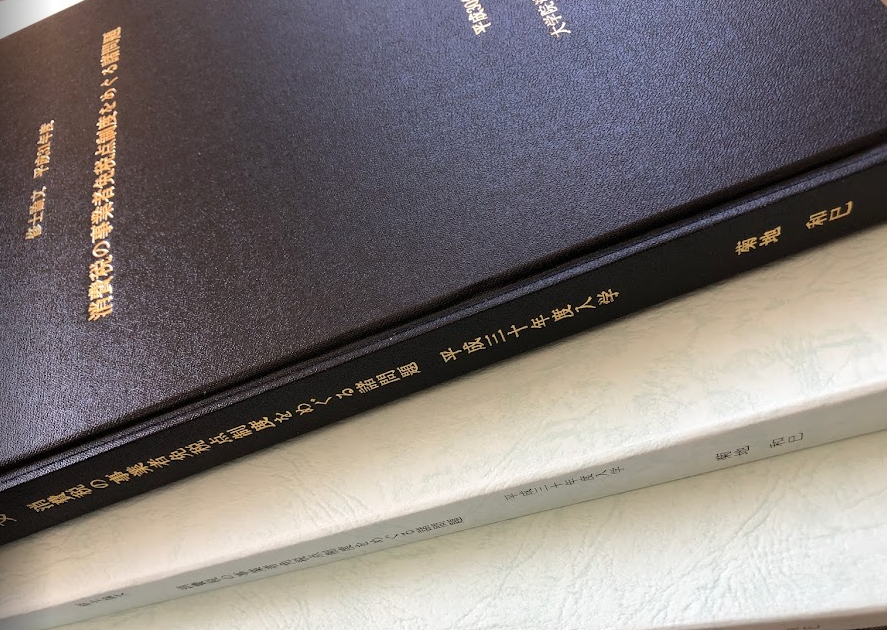
第1項 裁判の内容
名古屋地方裁判所 平成21年11月5日判決64
【事案の概要】
本件は、衛生用陶磁器の製造及び販売等を業として行う原告の代表者が、別会社を複数設立し、原告が取引先から請け負った業務をその別会社に外注委託し、原告が取引先から請負代金の支払を受けると、原告の取り分を差し引いて、残りを別会社名義の預金口座に送金するという経理処理を行うことで、原告は、仕入税額控除として、別会社の外注加工費に係る消費税額が控除されることになり、別会社に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は、新たに設立された法人65の事業者免税点制度により、すべて免除されるという方法により、順次、ある別会社の設立後2度目の決算期を迎えた後は、別の別会社を新たに設立し、その会社に外注委託するという処理を繰り返していたが、平成12年10月1日から平成17年9月30日までの各課税期間に係る消費税等について平成18年12月4日、修正申告66したところ、処分行政庁から平成19年3月27日付で重加算税の賦課決定を受けたことから、これらの賦課決定の取消しを求める事案である。
【原告の主張】
1.原告代表者(以下、Xとする)は顧問税理士に、消費税の節税方法について相談し、顧問税理士は、原告の業務の一部を分離して別会社を作り簡易課税制度を利用することを検討し、名古屋国税局税務相談室に赴いて相談し、同相談室の職員から、[1]新たに別会社を作って原告の外注委託先とするのであれば、別会社を法人として設立登記しなければならないこと、[2]原告の従業員を別会社に移して請負業務に従事させるのであれば、原告の従業員を退職させ、別会社で雇用しなおさなければならないこと、[3]従業員の給与は別会社から支払わなければならず、源泉徴収簿も別会社できちんと備える必要があること指摘され、[4]新しく設立する別会社の経理事務を原告の経理担当者が行っても問題はないとの説明を受けたため、上記指摘や説明を守って、営業していたものである。
2.平成15年5月、原告は半田税務署の税務調査を受け、実態を包み隠さず関係資料を全て提出し、調査に応じたところ、同職員から、税務上の問題点は指摘されなかった。調査に赴いた半田税務署の職員は、本件税務調査において、[1]別会社は実際には何らの業務もしておらず、別会社の代表者は単に名前を貸しただけであったこと[2]別会社に外注委託するようになった後も、請負業務はすべてXの指示の下で行われ、請負業務に係る売上げ、経費及び利益はXが一体的に管理していたこと、[3]外勤社員については、原告の名前で募集し、Xが採用を決定していたこと、[4]原告と別会社との間で、外注委託に関する契約や取決めはなかったこと、[5]原告の取り分の率をXが決めていたことの各事実を、認識し又は認識し得たものと認められるから、その上で同職員が税務上の問題点を指摘しなかった以上、原告としては、従前の納税方法が間違っていなかったと理解することは当然である。
3.以上のとおり、原告は、本件各賦課決定を受けた本件各課税期間の消費税等に関しては、本件税務相談の際に受けた説明に従って納税したものであり、また、平成15年5月の本件税務調査において「問題なし」との回答を得ているのであって、このような客観的事情が存する本件においては、原告が本件各確定申告において課税標準額に対する消費税額から本件外注加工費に係る消費税額を計算したことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当すると考えられる。
したがって、本件は、その全額について、国税通則法65条4項所定の「正当な理由」67があると認められるから、そもそも過少申告加算税の賦課要件を満たしておらず、本件各賦課決定の全額が取り消されるべきである。
また、仮に「正当な理由」が認められず過少申告加算税の賦課要件が認められるとしても、原告の申告行為には、隠ぺい及び仮装が存在しないため、重加算税の賦課要件は認められず、少なくとも重加算税の賦課に相当する部分は取り消されるべきである。
【裁判所の判断】
請求棄却
1.Xは、平成10年3月3日、3社の別会社を設立し、資本金はそれぞれ300万円とした。
2.Xは、同資本金に充てるため、原告の預金口座から300万円ずつ出金し、Xの預金口座を経由して各別会社名義の預金口座に振り込んだが、同別会社3社の設立後、別会社の預金口座から295万円ずつ出金し、Xの預金口座を経由して原告の預金口座に戻した。また、3社の取締役には、Xの内妻(以下、Yとする)、Yの父・母が就任した。
3.Xは、別会社が2度目の決算期を迎える前には、このまま消費税を支払わないで済ませたいと思い、更に別会社を作って従前の別会社への外注加工費を付け替えることにより、消費税等を免れようと考えた。新たな別会社の資本金は、前期2と同様に、原告の預金口座から300万円を出金した上で、最終的には原告の口座に戻した。また、新たな別会社の取締役には、Yの叔母が就任した。
4.Xはその後も同様にして、順次、ある別会社の設立後2度目の決算期を迎えた後は、別会社を設立し、その会社に外注委託するという処理を繰り返し、別会社に係る消費税等はすべて免除されるという処理をしてきた。
また、別会社の取締役は、Yの親族や親族の知人に名前を貸してもらったものであった。
5.別会社の経営実態等は次のとおりである。
①別会社の資本金
各別会社の資本金は、実際には、原告等の資金が原資になっており、しかもほとんどの別会社はその設立後に資本金の大部分を再び出捐者に返金していた。
②別会社の代表者
各別会社の代表者は、すべて、X又はYの親戚あるいはその親戚の知人であり、XはYの父と母に対しては、2人で月額20万円を支払っており、別会社のそれ以外の取締役に対しては、月額5万円を支払っていた。
③別会社の本店所在地
各別会社の本店所在地は、別会社の代表者の自宅としていたが、各自宅には、実際には別会社の事務所はなかった。
④従業員の転籍
Xは、原告の外勤社員を取引先ごとに別会社に割り当てて転籍させ、それぞれの割当先から給与を支払うこととした。
⑤別会社の経営判断等
別会社の実質的な経営者はXであり、請負業務はすべてXの指示の下で行われ、請負業務に係る売上げ、経費及び利益はXが一体的に管理していた。
外勤社員の採用や給与、経理処理等の事務は、すべてXの指示のもとにYをはじめとする内勤社員が行っていた。別会社の帳簿、通帳、社印やゴム印など別会社に関するものはすべて原告が保管し、Yが経理担当社員としてこれを使用していた。
⑥取引先からの売り上げの分配
取引先からの売上げの原告と別会社の取り分については、売上金額にXが決めてYに伝えた一定の取り分率を乗じた金額を原告の取り分とし、その残りを別会社に対し外注加工費として支払い、別会社の売上げとすることとしていた。
Xは、この原告の取り分率については、別会社から支出する経費と原告の利益状況とのバランスを考慮して、0.095あるいは0.1といったように何度か取り分率を変更していた。
⑦原告と別会社との間の契約等
Xは、別会社についても実質的な経営者であったから、原告と別会社との間の取引内容はXの一存で決定されており、別会社がそれぞれ発行するはずの原告に対する外注加工費の請求書は作成されていなかった。
6.Xは、本件税務調査の際に半田税務署の職員から原告と別会社の取り分率を決める基準につき質問を受けたことから、本件税務調査後は、顧問税理士の指導に基づき、帳簿上、取り分率を0.12と引き下げて統一することとし、その後もこれを変更しないこととした。
もっとも、原告の取り分率が下がり、原告の経費を支払うのが困難になったことから、原告から別会社への送金は、帳簿上の外注加工費の計上額とは関係なく、別会社からの経費の支払の必要に応じて、適宜送金していたため、外注加工費の計上状況と実際の送金状況とが大きくかけ離れることとなった。
7.前記1~6のとおり、原告ないしXは、何ら実体のない別会社を次々に設立し、これら別会社に原告の従業員を転籍させたように装い、また、別会社との取引が正当なものであるかのように架空の業務委託契約書を作成するなどして、原告の請負業務を別会社に外注委託したかのような事実を作出し、別会社に対する本件外注加工費の支払があったかのごとく仮装した経理処理を行っていたのであって、これらの行為は、国税通則法68条1項にいう「隠ぺい」又は「仮装」に当たるものと認められる。
したがって、原告の主張には、理由がない。
- 64 TKC法律情報データベース『LEX/DBインターネット』文献番号25500806 株式会社TKC HP
- 65原文では「新設法人」とされていたが、本論文では、法第12条の2第1項における新設法人(基準期間がない事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)と区別するため、「新たに設立された法人」とした。
- 66原告は平成18年8月1日、名古屋国税局による査察調査を受け摘発された。
- 67「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいう。(最高裁判決 平成18年10月24日 民集60巻8号3128頁)