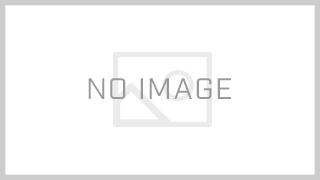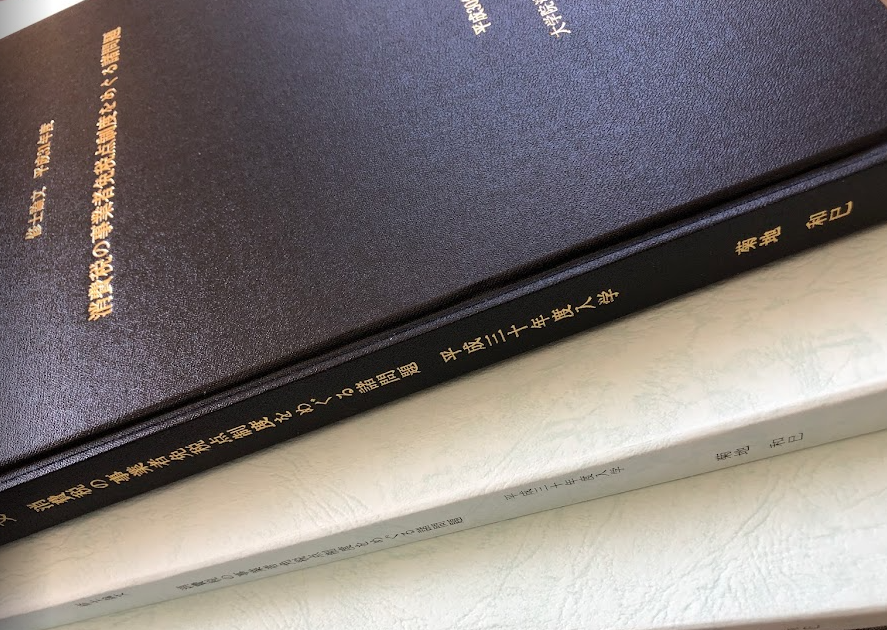
本事例では、原告が主張するように、法9条1項が消費税法の「基本的な趣旨や社会通念に反し、同法の立法目的を著しく逸脱したもの」とは考えられず、主張内容に「無理があり、判決内容は当然[70]」とする岩﨑教授の指摘が正しいと思われる。
また、原告が主張するように「課税売上高が3000万円以下であるか否かを、課税期間における課税売上高で判定することとなると、当該課税期間が終了するまで、納税義務が免除されるかどうか判明せず、消費者に消費税を転嫁すべきか否かの経営方針、消費税課税事業者を選択すべきか否か、簡易課税を選択すべきか否か、等々の判断がすべて後手にまわり、返って不合理な結果になることは明らかといえる[71]」とする実務的な視点も重要である。
他方で、原告が主張する「ある事業者の課税期間の課税売上高が3億円であっても、基準期間の課税売上高が3000万円以下であれば、納税義務は免除され、3億円の5%にあたる150万円が納税されず収益金となることには、納税者の理解と納得は得られない」という見解には、一考に値する部分も少なくはない。
それは、資本金が1000万円以上の法人であれば、「現行消費税法によれば(中略)、第1期は課税売上高が300万円であるが課税事業者、第2期も課税売上高が800万円であるが課税事業者、第3期は当該課税期間の課税売上高は4000万円であるが、基準期間の課税売上高が300万円であるので免税事業者、第4期も当該課税期間の課税売上高は1億円であるが、基準期間の課税売上高が800万円であるので免税事業者となり、課税期間における不公平性が存在[72]」していることによると思われる。この基準期間の問題は、改めて第4章で掘り下げることにする。
[70] 岩﨑健久「消費税法の免税点制度に関する判例研究」 帝京経済学研究 第38巻第1号(2004年12月)176~179頁
[71] 三浦道隆 前掲(注)62 148頁
[72] 岩﨑健久 前掲(注)70 178頁