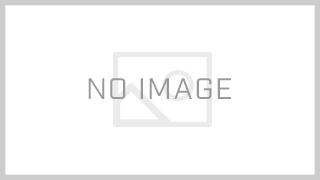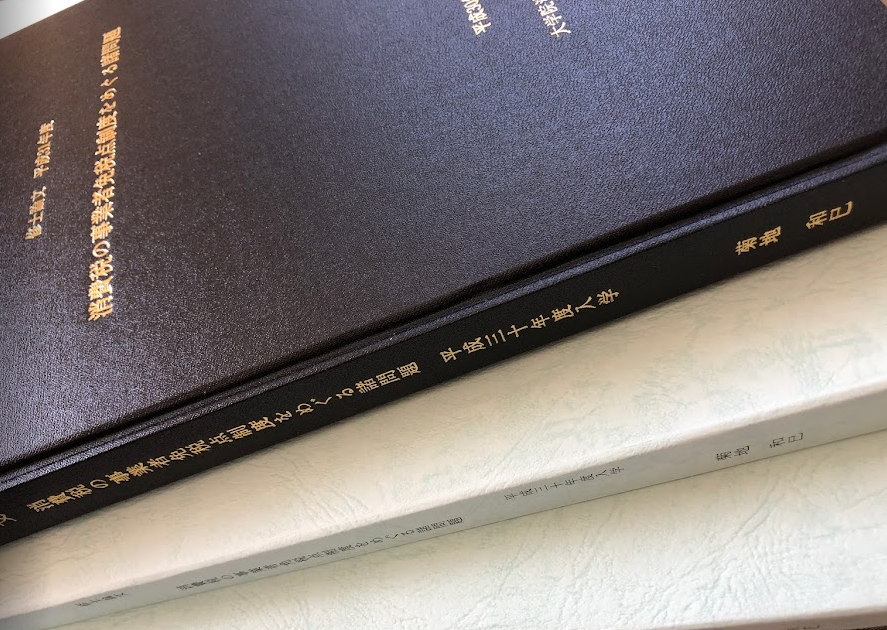
1.本件の争点は、課税期間に係る基準期間において免税事業者であった者について、当該課税期間に免税事業者に該当するか否かを判断する場合、基準期間における課税売上高の算定に当たり、課税資産の譲渡等につき「課されるべき消費税に相当する額」を控除すべきか否かである。
消費税導入当初は「実務家、研究者においても控除説は決して少数意見ではなかった上、課税庁が行う講習等において、あるいは課税庁による個別の指導においても、消費税相当額を控除して計算するよう説明された、とする多くの証言も存在する49」という。租税実務上は、本事件の更正処分直後の平成7年12月25日付の基本通達50において非控除説の立場が示された51。
2.また、この最高裁判決により、非控除説によることが確定したが、学説は、控除説と非控除説とに分かれており、両説の論拠は、森英明調査官の論文52に詳しい。
ここで一部を紹介すると、控除説の立場をとる田中教授は、法9条が「事業者」を課税事業者と免税事業者を明示する事無く、使用している点を指摘した上で「判決の考え方によれば、実際に3090万円の売上げをもつ課税事業者に匹敵するのは、実際に3000万円の売上げをもつ免税事業者だとするが、これは明文の根拠規定なく、ダブルスタンダードを持ち込んで、理由なく免税事業者を不利に扱うものであって、これこそ租税法律主義違反というべきであろう」53として、厳しく批判している。
また、森下教授は、「『免税事業者を消費税メカニズムの適用除外とする』という基本理論からすれば、免税事業者を『消費税相当額を転嫁すべき立場にない』と位置付けるのは当然の帰結であると考える。しかし、租税法律主義の観点からすれば、事業者の属性によって異なる計算方法を適用するためには、消費税制度の理論上は当然の帰結であったとしても、立法論として、やはりその具体的な取扱いの差異を消費税法上に確定的に規定しておくことが望ましいのではないか」54と提言されている。
3.筆者が思うに本事例の問題点は、控除説・非控除説について「法文からはどちらの解釈も成立する余地があり、また制度趣旨から一律の結論が導き出せない」55という曖昧かつ不親切な法の規定ぶりにある、と考える。その点で湖東教授は、「諸外国においては免税水準等につき税込みか否かを法規定において明確に示している。英国とフランスの場合課税売上高に税を含めず、ドイツの場合税を含めたところの金額としている。」56として、我が国の消費税法も諸外国に範を取って「解釈通達等ではなく法改正により直接かつ明文で規定すべきである。そうすれば租税法律主義の要請に適うとともに納税者に法的安定性、予測可能性をもたらし、今回の事件のような無意味な係争は生じない」57とし、「ドイツが規定するように、消費税法9条1項を『事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高(消費税に相当する額を含む)が三千万円以下である者については……』とすべき」としている。
4.判決当時は、免税点が1000万円に下がった58ことで、この問題は「実務的には、この判決に影響を受けることは少ない」59との声も上がっていたが、税率が10パーセントとなり、更なる増税が見込まれる今日において、むしろ影響が大きくなっていると考えられる60ため、早急に解決すべき問題であると思われる。
また、最高裁判決は、同水準の課税売上高を保つ事業者が、2年ごとに免税事業者と課税事業者の「ぐるぐる回り」が生ずるという問題61について何ら明確な答えを出していない。この2つの問題については、後ほど章を改めて改善点を探っていくことにする。
5.また、裁判では問題にならなかったが、「本判決は、課税資産の譲渡等を行った事業者の立場からの考察のみであり、課税資産の譲渡等の相手方である仕入事業者の立場からの考察はしていないという点を指摘しなければならない」として、「免税事業者の課税資産の譲渡等の受け取り対価の総額の中には消費税相当額が含まれておらず、その相手方の支払対価の総額の中には消費税相当額が含まれているという整合性の無さが、最高裁判決が下された現在においても完全に納得し切れない専門家がいるという原因の一つでもあると考えられるのである」62という声も聞かれた。
このような「免税事業者からの仕入れについても、課税事業者における仕入税額控除の対象となる」現状について、「消費課税理論上、説明できない重大な例外を認めていることで、このような「二分論」に基づく消費税の課税システムが十分には機能しておらず、経済的側面のみならず。課税理論的な側面においても、制度上の重大な欠陥が黙認されている状況にある」63という問題についても、後の章で改めて考察してきたい。
- 49 金井恵美子「基準期間において免税事業者である者については、基準期間の課税売上高の算定上免除された消費税相当額は控除できないとされた事例」 税務事例436号(2006年1月)20頁
- 50 基通第1条第4項第5項 (基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高) 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。
- 51 「このような新取扱いを本件に遡って適用することは、信義則に違反し、違法・無効である」とする主張する論者もいる。 北野弘久『税法問題事例研究』 勁草書房(2005年9月)402頁
- 52 森英明「時の判例」ジュリスト1303号 有斐閣(2005年12月)144頁
- 53 田中治「消費税をめぐる判例動向とその問題点」 税法学第557号(2007年5月)231頁
- 54 森下幹夫「消費税法における納税義務者に関する一考察」 岡山大学経済学会雑誌48巻2号(2016年11月)141頁
- 55 菅納敏恭「免税事業者の基準期間における課税売上高の計算-張江訴訟」税研148号 日本税務研究センター(2009年11月)174頁
- 56 湖東京至『消費税法の研究』 信山社出版(1999)120~121頁
- 57 湖東京至 前掲(注)56 118~119頁
- 58 平成16年4月1日以後開始する課税期間から、事業者免税点は3000万円→1000万円に引き下げられた。
- 59 多田雄司「事業者免税点の判例からみた消費税の本質」 税務弘報53巻6号(2005年6月)148頁
- 60 税率10%時代では、仮に1000万円に若干満たない売上の事業者が免税事業者であったとした場合(仕入税額控除が殆どない業種を想定)、90万円近い益税が生じる可能性があり、看過できない金額になると思われる。
- 61 橋本守次「消費税の免税点の判断に係る判例の検討」 税務弘報55巻6号(2007年6月)146頁 三木義一「免税事業者の基準期間における課税売上高の意義」 税務QA 37号(2005年4月)44頁
- 62 三浦道隆『消費税法の解釈と実務(増補改訂版)』 大蔵財務協会(2006年7月)172~173頁
- 63 森下幹夫 前掲(注)54 141~142頁