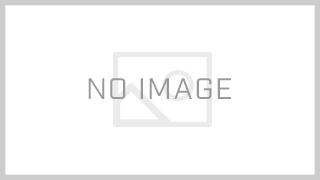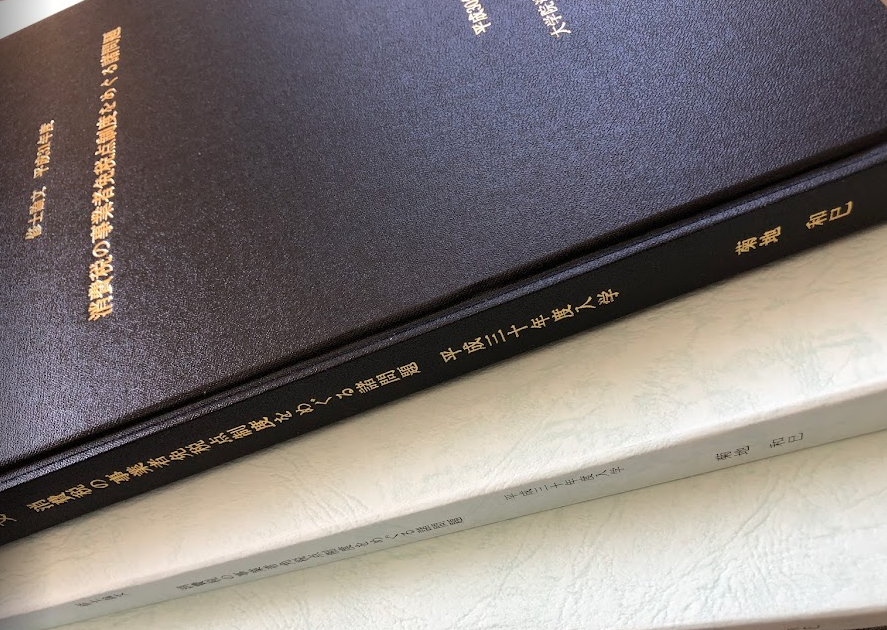
1.まず、第1項で取り上げた平成6年の税制改革は、資本又は出資の金額が1000万円以上の新設法人について納税義務を免除しないこととし、新たに設立される株式会社34は、事業者免税点制度の対象外とされた。これは、免税点制度の趣旨(小規模事業者の事務負担)を鑑みるに、「特に規模の大きな法人が新設された場合については、新設された後の2事業年度について免税とする必要はない35」という考慮によるものであり、その効果はあったものと思われる。また、判定基準として資本金基準36が採用された点は、「相対的に資本金が大きければ売上高も大きく原則基準(売上高基準)との均衡が図れるといった観点から基準期間のない課税期間における免税点の判定基準としては、最も合理的な基準と考えられる37」として、評価する声があった。しかし、後に「会社法の制定38にともない最低資本金制度がなくなり、1000万円を下回る資本金の株式会社の設立が容易になったため、あえて資本金1000万円以上の法人を設立する必要がない場合には資本金1000万円未満の法人を設立し、新設した法人に特例が適用されないようにした例が多いものと推測してよい」として、本改正の効果が有効に機能していないと思われる状況39を佐藤教授は指摘されている。この状況は、未だ大きくは変わっておらず、この点は後の章で考察を加えていくことにする。
2.次に、平成15年度改正において、ついに免税点は1000万円に引き下げられることになった。これにより納税申告件数は、佐藤教授によると「平成16年度の約202万件から平成17年度には約356万件へと約1.8倍、実数にして約154万件の増加を見せ」ており、「これにより納税義務を負う事業者が全事業者に占める割合は飛躍的に増加したと考えられる40」という(次頁図1を参照されたい)。この引き下げについては、「一定の前進と評価できる」が、「なお4割近い事業者が免税事業者に残るという問題41」が残り、依然として「事業者と消費者の対立を招いている」とする厳しい意見も聞かれた。
筆者は、この点に関し、宮島教授の「一定の前進と評価」すべきという意見に同感であり、この時点では、事業者免税点制度の問題に切り込んだ改正として十分なものであったと考える。

3.平成23年度税制改正では、従来の基準期間に加えて、特定期間による判定を追加することで、より機動的な免税事業者の判定を行うことができるようになった点で、評価することができる。ただし、この改正は「単に課税事業者になるのが早まっただけの改正」であり、「課税事業者から免税事業者になるときは、従来通り2年前(又は2事業年度前)で判定することに変更はなかった42」として、改正が「課税の適正化」の趣旨と矛盾しているという説もあり、この問題については、第3章第2節で改めて取り上げることにする。
4.社会保障・税一体改革では、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例について、新たに定められた。これにより、人材派遣スキームの一端は規制することが可能となったが、いくつかの抜け道がある改正となっており、その点についても第3章で扱うことにする。
34 1990年改正商法は、株式会社の最低資本金制度を導入し、1000万円を最低資本金としていた。
35 佐藤英明「序章 消費税の軌跡-導入から現在まで」日税研論集第70号 日本税務研究センター(2017年1月)12~13頁
36 他には、従業員基準、当年の見込み課税売上高基準等が考えられる 武田昌輔監修前掲(注)1 1783の2頁
37 武田昌輔監修前掲(注)1 1783の2頁
38 平成17年6月に成立し、平成18年5月施行された。
39 会社設立時の資本金の額について1000万円未満で設立し、免税点制度を有効に活用しましょう、と提案する税理士・コンサルタントのサイトがインターネット上に散見される状況である。
40 佐藤英明 前掲(注)35 11~12頁 図1も同論文によるものである。
41 宮島洋『消費課税の理論と課題(二訂版)』 税務経理協会(2003年12月)9~11頁
42 秋山高善「わが国消費税法における課税事業者となる時期の問題-平成23年度税制改正の検証-」共栄大学研究論集第10号(2012年3月)163頁