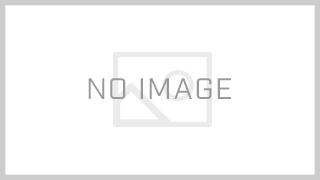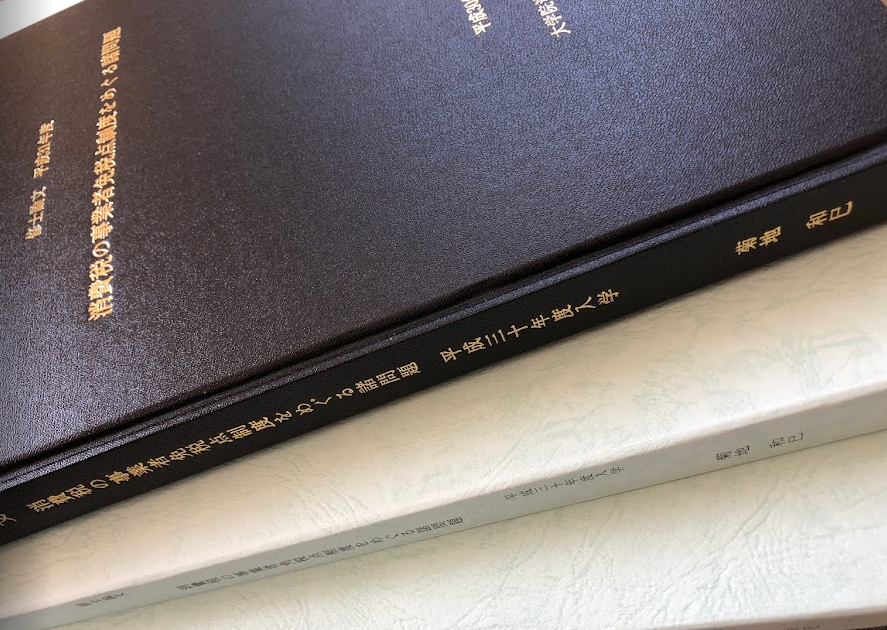
わが国に消費税が導入されるまでには、様々な紆余曲折があった。その様子は、山田教授の論文8に詳しい。簡単にその流れを紹介させていただくと、大きくは3つの段階に分かれ、「一般消費税」「売上税」「消費税」の3段階を経ることになる。また、消費税導入当時の主税局長である水野元国税庁長官による表1 9も参考にする。

1.「一般消費税」構想
昭和49年10月にオイルショックによる景気低迷により落ち込んだ税収を補うため、内閣総理大臣から税制調査会に対し諮問がなされ、昭和52年10月に「今後の税制のあり方についての答申」がまとめられ、製造者消費税、大規模売上税など8類型が検討された。これを受けて昭和53年12月、税制調査会は「昭和54年度の税制改正に関する答申」をとりまとめ、「一般消費税大綱」として多段階累積排除型の付加価値税である新税の骨格(税率5%等)が示された。事業者免税点制度については、「円滑な納税協力が得られるか」「事務的な負担に耐えられるか」という観点から検討し、「家族経営的な小売業者など」については免税事業者に該当することとし、具体的には、年間売上高が2000万円以下の小規模事業者を免税事業者とすることとされた10。家族経営的な小売業者を想定すると2000万円という金額はやや高いという印象を受けるが、それほど極端な金額ではない、と筆者は思料する。
その後の昭和54年10月の衆議院解散総選挙において、当時の大平総理が財政再建の必要性を説く中で「一般消費税」について触れたところ、中小企業者や野党から多くの反対意見が寄せられて、結局、断念せざるを得なかった。
2.「売上税」構想
昭和60年9月、中曽根総理から税制調査会に対し税制全般の抜本的見直しについての諮問がなされ、税制調査会は13か月間にわたる審議を行った結果、昭和61年10月に「税制の抜本的見直しについての答申」を取りまとめ、新しい間接税として、製造業者売上税、事業者間免税の売上税、日本型付加価値税の3案の仕組みが示され、選択の幅を持った形で取りまとめられた。
その後、同年12月に自由民主党税制調査会が示した「税制改革の基本方針」が取りまとめられ、事業者免税点制度については、課税売上高1億円以下の中小零細事業者を非課税とすること等が示された。水野元国税庁長官は、免税点について「一般消費税大綱では年間2000万円であったが、これを一挙に5倍に引き上げ、1億円とした。これによって、事業者の88%が免税となる。包括的、網羅的、普遍的な大型間接税はやらないという選挙公約等に配慮したものである11」として、免税点の水準が政治的配慮によるものであることを述べている。
山本税理士によると、昭和58年度ベースの試算では、課税収入年商1億円以下の者は、「企業数としては87.1%を占めるものの、売上高としてはわずか8.7%」にすぎないため「売上税の減収は少ない12」と述べるものの、零細業者の抱える問題点として、課税業者と非課税業者の立場をシミュレーションした結果、消費者が一般の消費者であれば問題ないものの、事業者が消費者の場合は、前段階控除ができないため、結果的に損になることがあることから、「年商が1億円以下であっても課税業者になった方が一般的に有利13」であると解説している。
売上税構想について、累積課税排除の方式が帳簿方式ではなく、税額票(インボイス)方式であったことから、取引排除の恐れにより、課税事業者選択への誘因は大きかったと思われる。しかし、前回の一般消費税構想から一挙に5倍の1億円という免税点は余りにも大きすぎ、免税事業者に該当する企業が87.1%にのぼっていたことも、課税の公平性の観点から健全な基準とは思われないため、実現性に乏しい案であったと、筆者は考える。
結局、「インボイス方式に対しては、産業界、特に中小企業の間で反対論が極めて強かった14」こともあり、国会での委員会審議が1回も行われることなく、廃案となった。
3.「消費税」の導入
売上税法案は廃案となったものの、税制改革論議は活発に続き、竹下新内閣の下、昭和63年4月「税制改革についての中間答申」が取りまとめられ、この答申を受けて昭和63年12月、消費税法案を含む税制改革関連法案が成立し、税率3%の消費税の創設に加え、所得税及び法人税減税、株式譲渡益課税の原則課税化、相続税の減税等、所得・消費・資産にわたる文字通り、抜本的な税制改革が実現した。
事業者免税点制度については、「『広く薄く』というこの種の税の性格や経済活動に対する中立性の確保の観点から、免税点については、3000万円とすること15」とされた。これは、免税点に限らず、世論の不評を買った「売上税との違い」を強調しようとする方向性で見直され、「結果として新税をそれだけ一般消費税に近づける議論になった」ためということである。その結果、「導入当時の調査では、個人・法人を含む全事業者の約65.7%(昭和61年の統計)が免税事業者にあたる16」状況となった。
売上税構想の1億円から見ると、3000万円は規模的には大幅に縮小され、穏当な数字に落ち着いたようにも見える。しかし、65.7%が免税事業者にあたる状況は、「経済活動に対する中立性の観点から」見て、正しいのであろうか、と筆者は疑問に思う。
4.金子教授は、この免税点制度について「①小規模零細事業者の場合には『消費税』を価格に含めて転嫁することは実際問題として困難であるという主張や、②小規模零細事業者に消費税の導入に伴う新しい事務や経費の負担が及ぶのを避けて欲しいという要望に応えて、『消費税』に対する反対をやわらげ、その導入を容易にするためにとられた措置」であると分析されているものの、諸外国と比べると免税点が高く、「免税事業者の範囲が広いため、税負担の転嫁が不透明であり、過大転嫁と過少転嫁の可能性」の問題17が起きていることも指摘されている。
以上、免税点が3000万円となった経緯について、消費税導入前史から遡り、その流れを確認した。その結果、3000万円という数字の根拠は、金子教授の指摘の通り、小規模零細事業者の事務負担に対する政策的配慮や、「3000万円という水準は、当初の消費税導入の際に徴税コストが重視されて落ち着いたレベルである18」という税務執行面への配慮に加えて、水野元国税庁長官の指摘の通り、売上税構想との違いを出すための政治的判断19として導き出されたものであることが判明した。これら全てを総合して落ち着いた金額が3000万円であると考えられる。
そしてこの金額は、「事業者の納税事務負担を軽減するための諸制度(帳簿方式、事業者免税点制度、簡易課税制度、限界控除制度)は、新税の円滑な導入に役立った20」として、評価すべき側面もあるという小池氏の説明は、大筋では正しいものであろう。反面で、「消費税の一部が事業者の手元に残るとされる『益税』への批判を招」くという状況も作り出していた。
そのため導入後は、事業者免税点制度についての見直しの機運が高まることになった。第2節では、その流れを追い、具体的な改正について触れることにする。
- 8 山田晃央「消費税の事業者免税点制度の在り方についての一考察」 税務大学校論叢第88号(2017年6月)35~49頁 本稿の作成にあたり、当論文を多くの点で参考にさせていただいた。
- 9 水野勝『税制改正五十年-回顧と展望-』 大蔵財務協会(2006年3月)506頁
- 10 水野勝 前掲(注)9 186頁
- 11 水野勝 前掲(注)9 380頁 同ページにて、中曽根総理の「多段階で大規模な間接税はやらない」といった国会答弁や、「国民も自民党員も反対する大型間接税はやらない」という選挙公約が背景にあった旨、述べている
- 12 山本守之『これが売上税だ!』日本法令(1987年2月)47頁
- 13 山本守之『売上税とその対策-新税対策のポイントと問題点-』税務経理協会(1987年2月)72頁
- 14 金子宏 前掲(注)4 16頁 なお、金子教授は、「最も重要な改革は、インボイス方式への切り替えである。それが実現したときにはじめて、わが国の消費税は、自他ともに国際的基準に適合したものとして認められることになろう」(同19頁)と述べられており、わが国も2023年にインボイス方式導入が予定されていることから、まさに金子教授の述べられる国際的基準に適合した制度へと進歩していることを評価できよう。
- 15 水野勝 前掲(注)9 506頁
- 16 金子宏『租税法(第19版)』 弘文堂(2014年4月)660~662頁 なお、同書第20版以降では、この部分(わが国の消費税の特色)の記述が省略され、第19版への参照を求める形になっている。
- 17 この過大転嫁と過少転嫁の問題は、本論考の重要な問題であり、益税と損税の問題として、第3章で詳しく取り扱う。
- 18 畠山武道・渡辺充『新版 租税法』 青林書院(2000年3月)261頁
- 19 消費税の税率、帳簿方式かインボイス方式かといった消費税制の根本的な部分から他の優遇措置(簡易課税制度・限界控除制度)とのバランス、更に言えば、他の所得税・法人税等の減税とのバランス等様々な角度で議論が尽くされた末の結論であり、筆者は導入当初の数字としては、妥当であったと考える。
- 20 小池拓自「消費税を巡る議論」調査と情報第609号 国立国会図書館(2008年2月)1頁